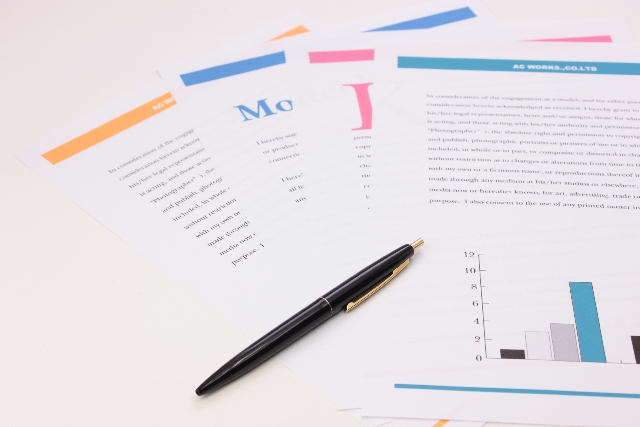


失業保険給付中のアルバイトについて
月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?
もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。
あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?
ご回答お願いしますm_ _)m
月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?
もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。
あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?
ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。
就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。
【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
不支給になった基本手当は繰越されます。
就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。
【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
この質問の回答には
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。
失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。
ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。
失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。
ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。
平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。
ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。
この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。
雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。
ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。
この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。
雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
失業保険を貰う為の手続きについて教えてください
現在ネットで調べているのですが、不明な点がありますので教えてください。
3月末で9年勤めた会社を退職します。
自己都合での退職です。
ネットでハローワークのページを見たところ、受給条件と言う欄に
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
?定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
?結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
今現在これに該当するのですが、例えば1年後や2年後に仕事が出来る状態になり、求職中の場合は手続きをすれば貰えるものなんでしょうか?
それとも離職日から一定の期間が過ぎると受給条件から外れてしまうのでしょうか?
現在ネットで調べているのですが、不明な点がありますので教えてください。
3月末で9年勤めた会社を退職します。
自己都合での退職です。
ネットでハローワークのページを見たところ、受給条件と言う欄に
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
?定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
?結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
今現在これに該当するのですが、例えば1年後や2年後に仕事が出来る状態になり、求職中の場合は手続きをすれば貰えるものなんでしょうか?
それとも離職日から一定の期間が過ぎると受給条件から外れてしまうのでしょうか?
すぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請ができます。
通常は受給可能期間は離職から1年間ですがプラス3年間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給することができます。
申請に必要なものは離職票、申請書(HWにあります)、妊婦なら母子手帳、病気なら診断書、印鑑です。
必要書類がわからない場合はハローワークに聞いてください。
通常は受給可能期間は離職から1年間ですがプラス3年間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給することができます。
申請に必要なものは離職票、申請書(HWにあります)、妊婦なら母子手帳、病気なら診断書、印鑑です。
必要書類がわからない場合はハローワークに聞いてください。
失業保険についての質問です!
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
〉前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。
それは所定給付日数の判断の話です。
受給資格の判断では
・最終の離職日以前2年間(1年間)に存在する、被保険者期間を数えます。
※「11日」には、有休など、出勤していなくても給与が支払われた日を含みます。
・前職の離職後、職安に離職票を出し、手続きをしていたなら、その前の期間は数えません。
それは所定給付日数の判断の話です。
受給資格の判断では
・最終の離職日以前2年間(1年間)に存在する、被保険者期間を数えます。
※「11日」には、有休など、出勤していなくても給与が支払われた日を含みます。
・前職の離職後、職安に離職票を出し、手続きをしていたなら、その前の期間は数えません。
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
普通は自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ただし、妊娠、出産、育児で退職する場合は、働くことが出来なくなった状態が30日続いたあと、1ヶ月以内で受給期間延長の申請をすれば基本1年+3年の受給期間延長ができます。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者(特定理由離職者)になって過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給ができます。
ただし、12月1日入社で5月31日以降に退職という丸々6ヶ月が必要ですし、退職の日から1ヶ月ごとに遡って見て11日以上勤務(有給は可能)している月が6ヶ月必要です。11日未満の出勤日しかない月は1ヶ月とは数えません。
ただし、妊娠、出産、育児で退職する場合は、働くことが出来なくなった状態が30日続いたあと、1ヶ月以内で受給期間延長の申請をすれば基本1年+3年の受給期間延長ができます。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者(特定理由離職者)になって過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給ができます。
ただし、12月1日入社で5月31日以降に退職という丸々6ヶ月が必要ですし、退職の日から1ヶ月ごとに遡って見て11日以上勤務(有給は可能)している月が6ヶ月必要です。11日未満の出勤日しかない月は1ヶ月とは数えません。
関連する情報